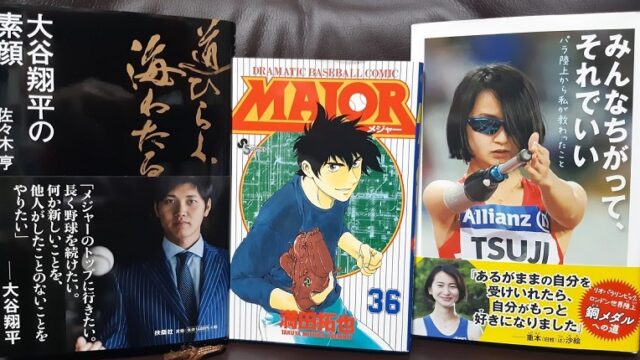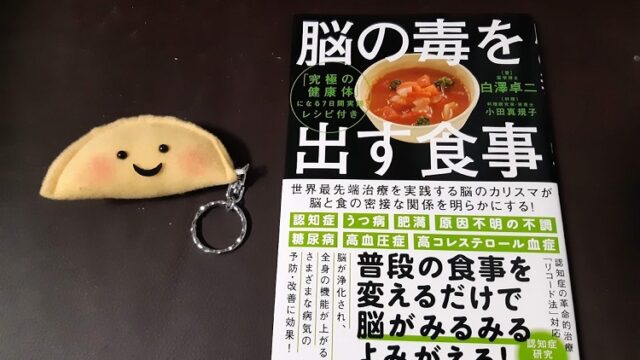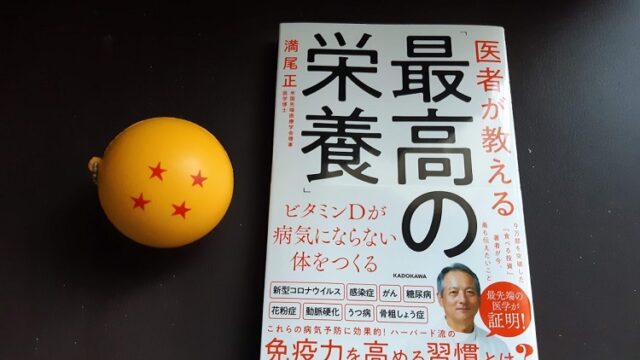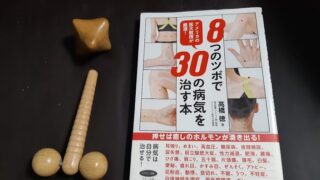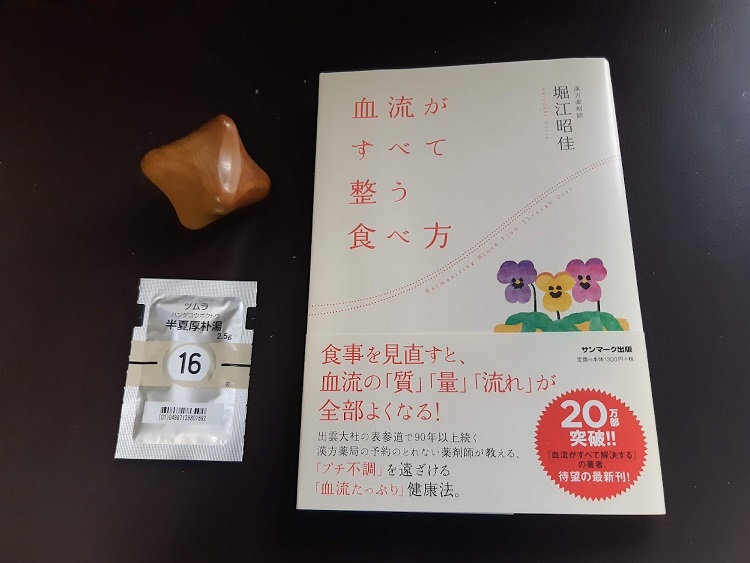
こんにちは、ゴローです。
本日の記事では、「血流がすべて整う食べ方」という書籍について書いていきます。
著者は、出雲大社参道で90年以上続く老舗漢方薬局の4代目。
薬剤師となったのちに、対症療法中心の西洋医学とは違う、東洋医学・漢方の根本療法に魅力を感じ方向転換しました。現在は、婦人科系の分野、なかでも不妊症を専門とする漢方薬剤師です。
自身の薬局で扱ってきた相談は、不妊の悩みを中心に、うつ・ダイエット・自律神経失調症など5万件を超える中で、著者がたどりついた答えが「血流をよくする」こと。この書籍の中では「食べ方」を中心に、血流をよくするための方法を述べています。
〇なんとなく不調が続いている方・慢性疾患に苦しんでいる方
〇不妊治療がうまくいっていない方
〇食べ方・食材を見直していきたい方
Contents
書籍の主な内容・目次の紹介
5万件を超える漢方相談を受ける中で、血流を増やすことの重要さに氣がついた著者。そんな著者の前作「血流がすべて解決する」は、大ベストセラーとなっています。
血流は、全身にある60兆個の細胞に酸素や栄養を届けるという大切な役割を担っているため、「血流を増やすことで、心と体のすべての悩みを解決することができる」といった内容の書籍が前作です。
こちらも大変参考になる本ですので、一度読んでみてほしいです。
そして前作に続き、血流の大切さを軸としながら、「食べ方」について書かれたものが今作となります。
血流、すなわち血の質・量・流れのすべては、わたしたちが食べたものに左右されています。つまり、「食」を見直していくことで、いくらでも血流は改善できるということであり、健康を含めた豊かな生活に繋がっていく!という内容になっています。
1章:血流が整えば、心も体もうまくいく
2章:胃腸を掃除して血流を整える「一週間夕食断食」
3章:血流を整える「食べたら出す」仕組み
4章:血流を整え汚染を防ぐ食材と食べ方
5章:血流は四季のめぐりと恵みで整える
6章:食べることとは、生きることである
血流を整える鍵は「食」への考え方と「胃腸」
食事を変えることで血流が変わっていくわけですが、大前提として「我慢する」・「罪悪感を持つ」といった食への意識を持たないようにしておきましょう。
食事のルールで自分を縛るのではなく、食べる喜びを感じながら、美味しく食べる習慣を作っていくことが大切です。
そもそも動物は、食べていくために最初の内臓である腸を生み出し、よりスムーズに食べるために神経細胞が生まれ、やがて脳へと進化していったように、人間にとって「食べること」は生きていく上でひじょうに重要なことだからです。
著者の経験上、血流そのもの以前に、体調の悪い人は「血液そのものが足りていない」そうです。そんな血流不足を解決するための鍵が、「胃腸」です。
胃腸が消化しきれない量を食べたり、砂糖たっぷりのお菓子などが胃腸を悪くしていきます。最近では、「リーキーガッド症候群」という、腸壁の粘膜に穴があくことによって、自己免疫疾患や過敏性腸症候群などの病気を引き起こしていることが問題になっています。
胃腸の不調があらゆる病気を引き起こしているということで、そもそも胃腸の状態をよくしていかないことには、血流の量を増やすことも、質をよくしていくことも出来ないということになります。
それでは、どのように胃腸の状態を改善していけば良いのでしょうか?
胃腸・血流を整えるための「一週間夕食断食」
そこで必要になってくるのが、「胃腸の大掃除」です。
胃腸には「捨てる」仕組みが備わっているのですが、それを可能にするのが消化管ホルモンの「モチリン」です。
そして、このモチリンの登場に欠かせないのが、食後約8時間の空腹時間です。そこでオススメなのが、1週間の夕食断食!
なぜ夕食なのかというと、漢方では午前5~7時が排泄の時間とされているため、朝に向けて、夜に胃腸の大掃除をしてもらうためです。
断食と考えると難しいかもしれませんが、たった1週間だけ、しかも夕食断食だけなら出来るような氣がしませんか?
たったこれだけのことで、胃腸が元氣になり血流が増え、同時に胃腸の汚れである痰湿がとれることで、血流がキレイになります。
さらに、夕食断食のあとの食事にも氣をつけて下さい。
断食のあとに善玉菌を応援する食事をすることで、腸内細菌の勢力図を塗り替えることができるからです!
ですので、善玉菌を優勢にしてくれる理想的な食事である「発酵食品」や「食物繊維の多い食品」を意識して摂取していきましょう。
血流を整え汚染を防ぐ食材
それでは最後に、胃腸を整え血流を整ていくための具体的な食材を紹介していきたいと思います。「医食同源」という言葉にもあるとおり、日々の食事こそが健康を守ってくれるものであり、もっとも格式の高い医師は、食べ物で健康を守る食医だとも言われています。
①七味唐辛子
血流をつくる鍵でもある胃腸を元氣にしてくれる食材がこれです!
すでに我々の生活の一部ともなっていますが、実は胃腸のための漢方薬といえるほどの薬効があります。
地域により多少の差はありますが、「唐辛子・焼唐辛子・粉山椒・黒ごま・陳皮・けしの実・麻の実」の7種類は、いずれも胃腸のための生薬なのです。
これは是非とも、生活の中に取り入れていきたい食材ですよね。
②玄米・雑穀
白いご飯から玄米・雑穀に変えていきましょう!
漢方や薬膳の世界では、気を補い、血を増やす食材とされているのが玄米や雑穀です。実際、栄養学の観点からも、玄米にはビタミン・ミネラルが豊富に含まれていて、完全食品といわれるほど栄養のバランスがとれた食品です。
白米というのは、玄米からわざわざ栄養がある部分を捨ててしまった残り部分です。考えたらおかしなことだと思いませんか?
僕自身、この事実を知ってからは基本的に玄米しか食べていません。白米に慣れてしまっている方も、続けるうちに玄米に慣れてくると思います。僕の場合、今では白米を食べると氣持ち悪くなってしまうこともあるくらいです(笑)
③「だし」をうまく利用する
体に悪いと分かっていても、砂糖や脂肪分の多い食事をしてしまうことは多いと思います。そんな時、問題を解決してくれるのが日本の伝統的な和食であり、「だし」です!
我々は、「糖の甘み・タンパク質のうま味・脂肪分」を感じると、脳の報酬系と呼ばれる回路が発動することで幸福感を得ます。このプログラムがあるからこそ、分かっていても白砂糖たっぷりのお菓子やケーキがやめられないんですよね。うん、よく分かる(苦笑)
ここでポイントになってくるのが、甘みはたくさんとらないと満足できませんが、うま味は少しの量でも満足感が得られるということです。これはありがたい!
そんなわけで、うま味を代表するアミノ酸である「グルタミン酸」や「イノシン酸」を含むダシを上手く利用していくことを考えていきましょう。具体的には、かつお節や昆布を使用した合わせダシなどになります。
以上、血流や胃腸を整えていくことの大切さ、そのための方法や食材などについて書いてきました。ここには書ききれなかった内容も、書籍の中にはいろいろと書かれていますので、皆さんの健康のためにも一度読んでいただけたら嬉しく思います。